
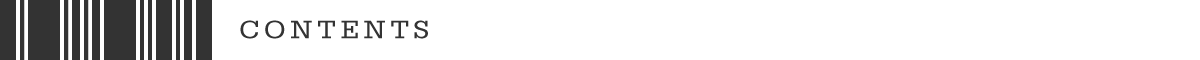
知性と身体性・空間性
知性と身体性・空間性
私は何かを学ぶとき、書物を手にする。Web上で同じ知識が得られるとしてもだ。なぜというに、書物という媒体から知識を得るほうが、どうも頭にしっかり定着するからだ。それについて考えると、「知性と身体性・空間性」の関係にいたる。
人間は知識社会へ移行してから、「脳」という器官に異様な権威を与えつづけている。脳をもって人間の格付けをするような思潮に違和感すら感じなくなっている。しかしそれは偏頗である。なぜなら人間は脳のみで浮かぶクラゲのような生命ではない。「人間」という機能は身体という全体性から生じるものだ。
また、私は何かアイデアがほしいとき、身体を使って「探索」する。パソコンやスマホの「検索」は、自分に合わせてソートされた不自然があり「探索」にはならない。たとえば本屋へ行くと、私のことなど意に介しない大量の書物が並んでいる。これは「自然」とよく似ている。あつらえられていない自然空間だからこそ「探索」になり「発見」があるのだ。
(前略)
神経系は、それを養う身体なしに、身体が呼吸する大気なしに、大気が包む地球なしに、地球がまわる中心にある太陽なしに生きている、と考えられるものだろうか。さらに一般的に言えば、孤立した物質的対象を想定すること自体が一種の背理を含んでいるのではないか。というのも、物質的対象は、その物理的諸特性を他の対象と取り結ぶ諸関係に負っており、そのさまざまな規定のいずれも、ということはつまり存在そのものすら、宇宙の総体において自分の占める場所に負っているのだから。
――
アンリ・ベルクソン/杉山直樹訳、『物質と記憶』講談社学術文庫、2019年
全体性を欠いた視座は井の中の蛙が見上げた空の欠片にすぎない。そこに見た空がいかに青かろうと、それは空を知ったことにならない。ひらけた空を見渡せば、北に雨雲、東に虹、西に太陽、南にムクドリの大群が空を覆い尽くすのを見るかもしれない。スマホの小さな画面はまさに偏頗な知識の欠片にすぎない。
私が書物を好むのは、単なる知識への接近のみならず、身体が共にあるからだ。本屋という空間での思いがけない邂逅にはじまり、気になる一文は表紙から指一本の厚みのあたりにあったとか、紙の薫りが良いとか――書物というものに身体全体を使って臨んでいるのである。
より純然な知性への接近は、頭一つで横着を決めこんでいてもできない。他の悉同様、総体的であるべきだろう。そして、ネットのあなたへのおすすめにアイデアとの邂逅を期待しないことだ。それでは傾向に偏り、より視野狭窄に陥るだけだろう。

書物は立体空間だ。そして視覚のみならず、嗅覚、触覚、さまざまな身体性を刺激する。それらが知識の記憶にも何らかの影響を及ぼしているのかもしれない。

自分に合わせてソートされていない自然空間にこそ「探索」があり「発見」がある。それは街であったり森であったり、さまざまだ。